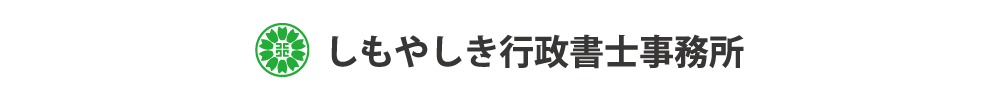建設業許可
建設業許可の取得に興味のおありの方へ
「建設業許可って何?」といった方に向けての発信になります。私自身が小規模事業者で、建設業許可を取得している会社の役員を務めています。建設業は、人々の暮らしを支え、社会に多大な貢献をもたらす素晴らしい仕事の一つ。
事業をさらに拡大し、安定した成長を目指すには、「建設業許可」の取得は検討に値すると思います。
許可を取得することで、主に以下の2つの大きなメリットが得られます。
1.【受注規模の拡大】より大きな仕事を受注できる
軽微な工事の枠(建築一式で1,500万円以上、その他で500万円以上)を超えた工事を請け負えるようになり、高額案件を獲得するチャンスが生まれます。
2.【企業の信頼性向上】対外的な信用力の向上
許可の取得は、法律で定められた経営体制、技術力、財産的基礎を満たしていることの証明であり、金融機関からの融資や、取引先からの信頼獲得に大きく貢献します。
私は、今からちょうど1年前、中国地方で建設中であったプラントの工事現場におりました。さらにその1年前は、九州のプラント建設工事現場におりました。そんな現場での経験に加え、過去に団体職員として、主に個人事業主の方々の建設業許可に関するサポート(もちろん無償)をしていた経験と、リフォーム会社に勤務していた経験から、比較的少数精鋭で建設業を営まれている、必要とする方へのお手伝いが出来ると思っております。
建設業許可の概要
| ❶ | 許可が必要な場合 |
| 建設業を営む場合にあっては、軽微な建設工事(※)のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受ける必要があります。 軽微な建設工事(建設業許可の適用除外)とは? ・建築一式工事 ⇒工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事又 延べ面積150 ㎡未満の木造住宅工事 ・建築一式工事以外 ⇒工事1件の請負代金が500万円未満の工事 (注)軽微な建設工事のみを請け負う場合でも、その工事が解体工事である場合は、建設リサイクル法による解体工事業の登録を、浄化槽工事である場合は、浄化槽法による浄化槽工事業の登録を受ける必要があります。 |
|
| ❷ | 大臣許可と知事許可 |
|
・国土交通大臣許可 ⇒2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする事業者 ・都道府県知事許可 ⇒1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする事業者 |
|
| ❸ | 許可業種 |
| ・工事の種類により29業種に分類されています。 (土木、建築、大工、左官、とび・土工、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体)工事業 |
|
| ❹ | 許可の有効期間 |
| ・5年間(有効期間満了の日前30日までに更新申請が必要です。) | |
| ❺ | 許可申請手数料(知事許可の場合)※青森県収入証紙での納付となります。 |
|
・新規:9万円 ・業種追加及び更新:5万円 ※概要は、青森県県土整備管理課様作成の資料を部分的に抜粋しました |
|
| 許可が必要な工事を無許可で行うと罰則があります。「3年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)」というものです。 | |
申請について
「要件をクリア出来れば1~2ヶ月で取得できます」としか申し上げられませんが、経験則でいえば、取得を前向きに検討されている事業者であれば、それほどハードルは高くなく、ほとんどの方がクリアできるのではないかという感じです。もちろん要件を満たしていることを裏付ける書類を提出する必要があります。
これまで、許可逃れを目的とする“分離発注”を得意げに話し「許可がなくても仕事が出来る」、「個人事業主だから」、「下請だから」、「手間と金がかかるだけ」、「施工の技術さえあれば良い」等、様々なお考えを持つ方とも接してきました。工事の品質と、許可や資格の有無は必ずしも比例しないことは現実としてあるかもしれませんが、法令を遵守して「土俵に上がる」資格を持たなければ、せっかく訪れたチャンスをつかめない可能性があります。
これまで、許可逃れを目的とする“分離発注”を得意げに話し「許可がなくても仕事が出来る」、「個人事業主だから」、「下請だから」、「手間と金がかかるだけ」、「施工の技術さえあれば良い」等、様々なお考えを持つ方とも接してきました。工事の品質と、許可や資格の有無は必ずしも比例しないことは現実としてあるかもしれませんが、法令を遵守して「土俵に上がる」資格を持たなければ、せっかく訪れたチャンスをつかめない可能性があります。
費用について
建設業許可は取得して終わりではなく、事業が継続する限り、義務や対応が求められます。それには相応の手間と費用が伴いますが、法令に基づく義務なので「費用が発生するから」「メリットを感じないから」といった理由だけで、保持しないことを自由に選択はできません。許可を取得して、維持していくための費用についてですが、専門家に委託をされても月額にならせば「それほど高額ではない」という認識の方がほとんどではないかと思われます。建設業許可の取得を前向きにご検討してみてください。